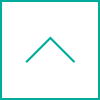里沼(SATO-NUMA)
「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺文化
「祈り」「実り」「守り」の沼が
磨き上げた館林の沼辺文化
令和6年度 館林市「日本遺産」推進協議会 議事録vol.02
令和6年度 第2回館林市「日本遺産」推進協議会(書面会議)結果
令和7年3月に、書面開催により第2回館林市「日本遺産」推進協議会を開催し、全委員よりすべての議案が承認されました。
【委員からのご意見及びご意見に対する回答】
❶
膨大な量の資料等の作成、本当にお疲れ様です。提出書類の様式があるとは言え、資料全体の構成、一つの項目の内容、記述の量ともすばらしく、担当者様の熱い思いに敬服しております。提出方、よろしくお願い致します。
→総括評価・継続審査を含め、委員の皆様にもお力添えをいただきながら、引続き日本遺産「里沼」事業を推進して参ります。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
❷
1 資料への意見
⑴議案書について
P1 本文下から5行目 「他分野」 ➡ 「多分野」の誤か。
→1⑴ご指摘いただいたとおり「多分野」の誤りとなります。お詫びして訂正いたします。
⑵「実績報告書」について
P1「様式1-①」個別評価が全て「可」 ➡ 評価の基準と判定表記についての説明が見つからなかった。達成率は100%超えなのに「可」で良いのか。さらに上位の判定評価は無いのか。
→評価基準の提示が漏れており申し訳ありません。文化庁作成の「日本遺産を通じた地域活性化計画実績報告書記入要領」において、個別評価(自己評価)については【可・不可】から選択することとなっております。従って日本遺産「里沼」における個別評価は全て【可】となります。
2 全体に及ぶ意見
⑴「インバウンド」対応について
①P6⑵「インバウンド来訪者」 ➡ 海外からの旅行者(来訪者)に限定しない方が良い。外国籍の市内居住・在学・就労が多い地域特性の点から、その家族・親族の来訪を促す方策も有効であろう。
②P7⑷「若者・外国人の意見を反映」➡ 外国籍の市内居住者・就労者から始めるのが着実であろう。
→インバウンドに関してはこちらも懸念事項として捉えており、具体的なご意見、大変参考となります。第2期地域活性化計画に反映させていただきます。
⑵向井千秋記念子ども科学館事業との連携について
①議案書・参考「実績報告書」を一見して子ども科学館事業との連携への言及が見当たらない。 ➡「第1期日本遺産「里沼」地域活性化計画」での重要な成果であり、館林の全市的な取組の姿勢として積極的に打ち出してよい。
②とりわけ「日本遺産「里沼」を活かした郷土愛の醸成での、「ROCKETの学び」を活かした「里沼プログラム」の実施」は実績として強調してよい。 ➡ 児童・生徒・学生の幅広い連携と段階的育成の取組と成果は「様式1-1」②―⑵「評価項目⑵取組内容」など各所に加えてよい。
→ご指摘のとおり「館林ROCKETプロジェクト」につきましては、第1期地域活性化計画報告書に追記させていただきます。令和5年度に当市を会場に開催した「日本遺産こどもサミット」での活躍など、「里沼」を通じた人材育成にも大いに寄与したプロジェクトであり、今後も協力して「里沼プログラム」を実施して参ります。
⑶地方史研究協議会館林大会の開催について
①「様式1-1」評価項目⑷―9への言及。
➡「こうした実績が認められ」では既にまとまったせいかを得ての開催のような印象がある。現時点の状況からは「こうした実績が注目され」の方が今後の取組への期待を込めた意味が強まる。
→ご指摘のとおり修正させていただきます。
②「様式1-1」評価項目⑷―9「具体的な取組内容」の指摘事項「里沼の普遍性や希少性、魅力あるストーリーの掘り下げを行うこと」の意味。➡ 全国各地に所在し一見するとさしたる印象をもたせることのない沼を、「里沼」としてストーリーをまとめたことが日本遺産認定での大きな要因となった。館林から「里沼」の普遍性(全国各地に所在するもの)と希少性(価値に気付かれないまま消滅していく懸念)を発信しいくことが期待されている。地域活性化計画で策定される種々の事業・催事の基本となるのが、「里沼」の歴史面(生成過程を含む)での学術的位置付けと文化財・文化資産としての価値づけあるが、全体的にその認識と取組が希薄に思える。
③館林大会での成果はその契機となり得る。 ➡ その成果を検証するとともに、より深化させる継続的な研究活動の実施を明示す必要がある。市史の専門委員会でも意見が出ている「里沼学」「里沼学センター」といった仕組みの創設を、「地域活性化計画」「令和7年度事業計画」で打ち出すのが得策ではないか。
→ご存じのとおり「第2期日本遺産「里沼」地域活性化計画」は2025~2027年度の計画となっております。本計画では「(1)将来像」において「里沼の普遍性と希少性」・「里沼学の確立」について追記したうえで、次期計画(第3期日本遺産「里沼」地域活性化計画:2028~2034年度)と同じく中期および後期計画(2028~2034年度)において、「里沼学」「里沼学センター」といった仕組みの創設を盛り込んだ「館林市文化財保存活用地域計画」と歩調を合わせて取り組んで参ります。
❸
館林市の貴重な文化資源が多くの人の目に留まり活用されることを願っていますので、今後3年間の活動におおいに期待しています。
→総括評価・継続審査を含め、委員の皆様にもお力添えをいただきながら、引続き日本遺産「里沼」事業を推進して参ります。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
❹
1.日本遺産「里沼」認定継続記念セミナーに関して
2月は事業が集中しているので、7月の審査結果公表(認定継続を前提として)直後の8月も想定できるのではないか。プレイヤー育成と考えると、学校夏休みという期間は育成のための連続講座が開きやすいのではないか(2月は大学・高校とは期末と入試に翻弄される)。
→認定継続後の人材育成セミナー開催について、この先を見据えたご意見ありがとうございます。今後の事業実施の参考とさせていただきます。
2.「里沼」旅行商品造成支援事業に関して
旅行業者の観光ツアー造成に対する支援事業(助成)と位置付けられているが、昨今の認定評価を見ると、インバウンドを中心とした観光客数の増加が評価の大きな基準になっているように見える。そのことを考慮すると、インバウンドないし首都圏からの観光客増加に繋がるモニターツアーが不可欠と思われる。また、そうした視点で進めば、観光庁のかなり大きな助成も見込まれる。そうした助成を得られることも評価の支えとなる。そのことを意識した支援事業とされることを期待する。
→ご指摘のとおり、日本遺産制度は文化庁事業でありながら観光面での取組が重視されております。観光事業化におきましては、観光部局や民間事業者の主導により、インバウンドや首都圏からのモニターツアーといった視点を持って取り進めて参ります。
❺
【意見】
様式1-2(5)観光事業化の取組内容には、多々良沼公園に隣接する館林美術館・総武鉄道館林駅を結ぶ路線バスの発着時間を、東武鉄道の特休列車である「りょうもう号」の発着時間と合わせることで、首都圏から館林美術館と多々良沼公園への集合強化を図ったことについての記載をご検討願います。これは、館林市安全安心課交通防犯係が令和5年度に実施した素晴らしい実績であると考えます。
→ご指摘いただいた「りょうもう号の発着時間に合わせた路線バスの発着時間調整」につきましては、二次交通の利便性向上策として「様式1-2(4)整備」内に追記させていただきます。
【その他】
議案書に記載することではありませんが、今後、東武鉄道館林駅と館林美術館を結ぶ路線バスに多々良沼公園停留所を新設のご検討をお願いします。また、館林美術館と多々良沼公園への集客を強化するために、館林市の「彫刻の小径」をきれいにして、歩きたくなる場所にしていただき、館林美術館と多々良沼公園と彫刻の小径の周遊ができるようにご検討をお願いします。
→「多々良沼公園停留所の新設」と「彫刻の小径の景観向上」につきましては担当課へご連絡させていただきました。今後とも他部署と連携し、横断的な整備を進めて参ります。